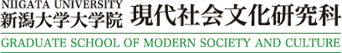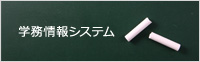2025年3月に博士学位を取得した田村優さんに、現社研での思い出を書き下ろしていただきました。田村さんは、中国に留学して博士論文を提出した後、アンゴラで就職、帰国後に現社研で再び博士論文を完成させた、という異色の経歴の持ち主です。<文化人類学>に軸足を置きつつ、世界を股にかけて活躍する姿をご覧ください。
現代社会文化研究科には、博士前期課程の頃から10年間お世話になりました。この場をお借りして、在学期間中、新潟、北京、アンゴラ、モザンビークと移動するなかで経験したこと、考えたことなどの想い出を綴りたいと思います。お付き合いいただければ嬉しいです。
(私の場合海外を転々としながらの研究生活だったため10年という長い年月がかかりましたが、ほかの方はもっと早く修了しています。これから大学院に進学される方がどうかご心配されることのないよう、念のため付け加えます。)
博士前期課程に入学した当初、私は農村社会学を専攻しており、新潟の「限界集落」と呼ばれていた山村のために何かできるのではないか、と意気込んでいました。でも実際に村を訪れ、村の人たちと触れ合うなかで気づいたのは、私の方が村の人たちに教わるばかりということでした。
南魚沼の山村の人たちは、過酷な豪雪地帯において、環境と調和しながら生きており、独自の暮らしの知恵を培っていました。村の人たちが振る舞ってくれたフキノトウ味噌、山菜、キノコなどの美味しさは格別で、そうした新潟の山の「宝」を守る人びとを尊敬するとともに、何かを変えようとする前に、まずその土地や人びとの文化、そして生活について深く理解する必要があると痛感させられました。

調査地の山村にある鎮守社が雪で埋もれる様子
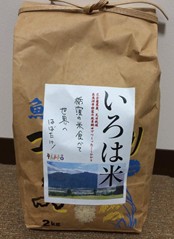
村の人が送ってくださった新米(とても美味しいです。おすすめです)
こうした経緯もあり、博士後期課程では専攻を文化人類学に変更し、フィールドも日本の農村から、以前から縁のあったモザンビークの農村へと移すことになりました。文化人類学の基礎を学んだのち、中国からアフリカを見てみたいと考えていたところ、中国政府奨学金の奨学生として北京市に留学する機会をいただき、新潟大学を休学して中国農業科学院へと進学しました。自主的なダブルディグリーの始まりでした。
北京での研究生活が始まるとたくさんの驚きがありました。院生たちは、研究室で大半の時間を過ごし、ものすごい速さで論文を出し、脇目も振らず全力で研究に打ち込んでいました。毎朝6時くらいには研究室に来て、指導教員に与えられたタスクをこなした後、自分の研究に打ち込み、昼食は学食や出前で簡単に済ませ、デスクに突っ伏すかたちで昼寝をして、夕食後もそのまま夜の10時頃まで研究室にこもるという生活をしていました。中国のように人口が多く、競争が激しい社会で業績を出すというのはこういうことかと、とても驚かされると同時に、自分ももっと努力しなければならないと気持ちを新たにしました。
そのように多忙な日々のなかでも、研究室が一緒だった院生たちは私を北京の観光名所に連れ出してくれました。北京では2年半暮らすことになりましたが、彼らのおかげで研究面でも、生活面でもとても有意義な時間を過ごすことができました。友人たちに感謝しています。

北京市にて、研究室の友人たちと
中国農業科学院では、たびたびアフリカ諸国、アジア諸国をはじめとする国から研究者や政府関係者が訪れることがあり、国際会議の運営に携わる機会にも恵まれました。なかでもYPARD(Young Professionals for Agricultural Development)の日本代表の一人として農業開発関連の活動に参加させていただいたことは大きな学びとなり、国を超えて農村と農村が直接つながることの重要さを実感することとなりました。

YPARDの定期会合にて
在学中、モザンビーク北部の農村での第一回目のフィールドワークを終え、農業経済学分野で大豆の契約農業に関する博士論文を執筆しました。博士論文は、Recontextualizing Contract Farming in Central Mozambique: The Case of Soybean Productionというタイトルで提出しました。
その後、就職のため、新潟大学を休学したまま中国からアンゴラへと移動し、在アンゴラ日本国大使館の専門調査員として働きました。当時はコロナ禍の真っ只中で、状況は非常に混乱していました。大統領令の翻訳や在留邦人の帰国支援に追われ、最初の1年間はほとんど調査を行うことができませんでした。翌年以降状況が落ち着いてから、コロナ禍前後での経済状況の変化などについて調査し、報告書をまとめることができました。また国際機関との調整業務に関わらせていただく機会もあり、それまで研究対象として外側から見ていた開発支援の現場を、内側から見る機会に恵まれました。
このような調査や業務を通じて、政府という立場から調査を行うことの難しさを痛感するとともに、外務省職員が各国政府との間で日々行っている調整業務の重要性を実感しました。彼らの地道な努力があってこそ、良好な外交関係が保たれているのだと思います。
アンゴラは産油国であり、アフリカ諸国のなかでは経済大国である一方、国内には非常に大きな格差が存在しています。海岸沿いの風景は一見、マイアミを連想させますが、少し路地を入ると、舗装されていない道路とバラックが連なる光景が広がります。月収が1万円の人と50万円の人が共存し、一食200円の食堂と一食4,000円のレストランが同じ道に並ぶ首都ルアンダは、まさに混沌としています。残念ながら、貧困や犯罪などの課題も多いですが、その一方で、日々をたくましく生きる人たちのエネルギーで満ちあふれた魅力的な都市です。

ルアンダの海岸部の風景

ルアンダの市場の風景
アンゴラは、自然豊かな国でもあります。その美しい景観には何度も圧倒されました。日本では知る人の少ない国ですが、2023年から日本国籍者の場合観光ビザの取得が免除になりました。ぜひ多くの皆さまに訪れていただきたい地です。

アフリカで二番目に大きいカランドゥーラの滝

ミラドウロ・ダ・ルーア(月の展望台)と呼ばれる地形が特徴的な観光地
3年間のアンゴラでの勤務を終えて帰国した後、文化人類学を学び直し、モザンビーク北部のフィールドへと戻り、婚姻と離婚についての調査を行うことにしました。ここから本格的に新潟大学大学院での博士論文執筆が始まりました。フィールドは、ロムウェ(lomwe)という母系相続や妻方居住婚を実践する人びとが住む山間部の村です。そこで出会った村人たちは、婚姻/離婚という私的な事柄について知りたいという迷惑極まりない私を、村の一員としてあたたかく迎え入れてくれました。

モザンビーク北部のフィールドの友人たちと①

モザンビーク北部のフィールドの友人たちと②
ロムウェは、ごつごつとした山、青く澄み渡った青空、そして一面緑色の畑に囲まれた絶景の地で暮らしています。私が調査を行っていた村は、多くの農業関連事業が実施されてきた肥沃な地であり、今では道路の舗装工事も進んでいます。そのような都市化が進む農村を対象に、主に裁判所での参与観察やインタビュー調査を行い、その結果を2024年度提出の博士論文『モザンビーク母系社会における夫婦愛の変容――婚姻関係の成立、揺らぎ、破綻に着目して』でまとめました。

村と街をつなぐ道路の風景

共同体裁判所と呼ばれる地方裁判所
博士論文を2本執筆するというのは、今考えればかなり無謀だったと思います。自主的にダブルディグリーをしようと思い立ったとき、もっとよく計画しておくべきだったと後悔することもありました。論文の執筆中には、もう書きたくないと研究室でひとり、泣いているようなこともありました。でも終わってみれば気楽なもので、後悔など微塵もなく、全力でやりきったという達成感でいっぱいです。
現在在学中、これから大学院への進学を検討している方々には、ぜひ、在学中にやりたいと思ったことにどんどん挑戦していっていただきたいです。その過程にはさまざまな困難があるでしょうが、終えた後にはきっと良かったと思えるはずです。(ただ、私のようにならないようよく計画してください。)
文系が脇に追いやられるような昨今ですが、国際的な視野で見ればまったくそんなことはないと思います。むしろ、Chat GPTなどのAIの活用がますます進む世の中だからこそ、自身の頭で考え、文章を紡ぎ出す文系の能力が求められているのではないでしょうか。世界各地で、文系ならではの強みを活かして仕事、教育、研究を行っている人たちが、大活躍しているのを目にしてきました。専門性を活かし、現社研出身の方たちが今後一層国内外で活躍していくことを願います。私自身も尽力していきたいと思います。
最後に、関心に応じてテーマ、フィールド、専攻をも変えていく私の意向を100%尊重し、柔軟に対応してくださった主指導教員である加賀谷真梨先生と中村潔先生、副指導教員の園田浩司先生、松井克浩先生に心より感謝いたします。また博士前期課程で指導教員を務めてくださった佐藤康行先生には、研究の基本の基の字から手取り足取り教えていただきました。先生方には、研究、生活ふくめ多方面から支えていただきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。日々の研究室の生活では、鈴木光太郎先生、石田純子先生、川西裕也先生、増田瑞穂先生に大変お世話になりました。その他、人文社会科学系の多くの先生方に、ティーチング・アシスタントや教務補佐等を通じてお世話になり、育てていただきました。厚くお礼申し上げます。
修了後は、教育者、研究者としての能力を磨きつつ、次の世代に先生方からいただいたバトンをつないでいけるよう努めていきたいと思います。本当にありがとうございました。
田村優